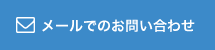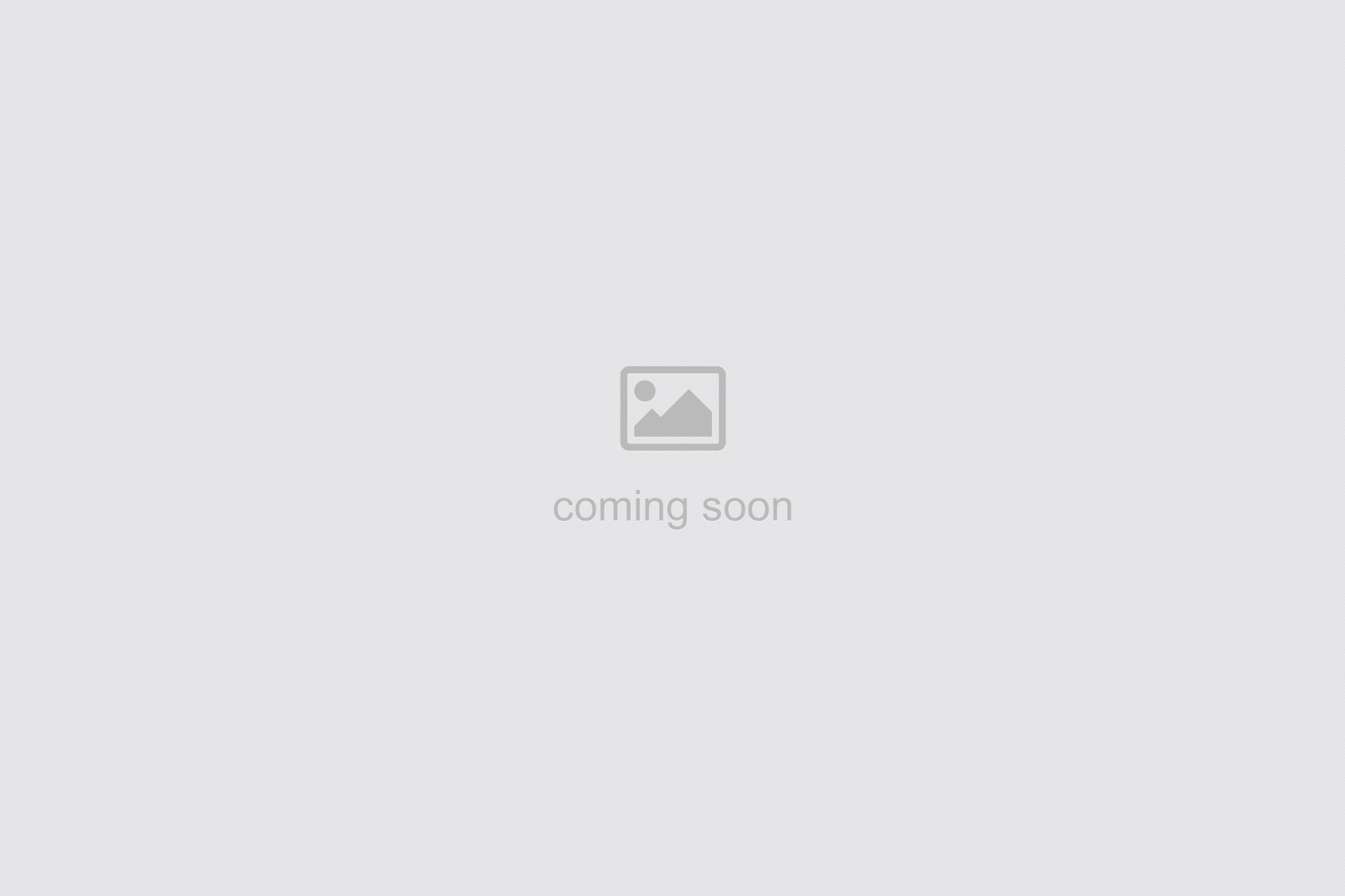所長の小部屋
憲法記念日
新緑が鮮やかな季節となりました。
5月3日は、憲法記念日です。
日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。その前文や九条には、平和への決意が込められています。
以前、平和学習で訪れた沖縄県の南風原町には「憲法九条の碑」が建っています。大きな石に力強い文字で「憲法九条の碑」と刻まれ、下の石には第二章「戦争の放棄」が記されています。
碑がある場所(広場)の近くには、アジア太平洋戦争の末期の沖縄戦で、陸軍の野戦病院として使われていた壕があります。この壕では、負傷した兵士や看護するために動員された高等女学校の生徒たちが、敵からの猛烈な攻撃の中で恐怖の日々を過ごしたり命を奪われたりしました。
その広場は、「鎮魂広場」と名付けられています。どっしりと据えられた「憲法九条の碑」は、「二度と同じ過ちを国に繰り返させてはならない」と強く訴えかけています。
「憲法九条の碑」は沖縄県に多くありますが、日本各地で設置される動きが起こっています。憲法九条の必要性を感じ、「憲法を活かしていこう」「残していこう」という市民の願いが広がっています。
今、世界各地で戦争や紛争が続いており、日本も抑止力の名のもとに防衛力強化へと突き進んでいます。国家による戦争の惨禍を再び起こさせないために、武力ではなく相互理解と対話を基盤とした平和を希求していくことが大切です。
所長 高橋 公子
アップデート
新年度のスタートを応援するように桜がさいています。
最近、アップデートが大事と思うことがありました。
赤ちゃんの離乳食を始める時、どのようにスプーンを使いますか。食べ物を口に運んだ後、スプーンを斜めに傾けて口から戻しますか。水平にして戻しますか。
わたしは、スプーンに食べ物が残っていると、スプーンを傾けて残りを口の中に入れてしまっていました。でも、スプーンを水平に戻すと、はじめは食べ物が残ってもそのうち赤ちゃん自らが口を前にもっていく食べ方ができるようになると最近知りました。ちょっとしたことですが、子ども自らが行動に向かうまで待つスプーンの使い方もあるのだと感心しました。
4月から就職する息子が気になっています。先日、見慣れないネクタイの結びかをしていたのでそっと調べてみました。いろんな結び方やデザインごとの使途があることが分かりました。生活の中でよく見るネクタイだけれど、自分を表現したり生活を楽しんだり方法がいろいろあるのだなぁと驚きました。
職場で、どの字体が読みやすいのかが話題となりました。わたしは、明朝体が読みやすくて好きなのですが、人によっては明朝体が点の集まりのように見える人や濃い字体が読みづらいと感じる人がいることを知りました。学校では、UDデジタル教科書体を使っていましたが、普段使う文字1つとってもよく考え選択して使う必要性を感じています。
日常の中の「普通」「常識」「これまで通り」という感覚。一度立ち止まって見直し、広く情報を集めながら、自らをアップデートしこうと心に決めた4月です。
所長 高橋 公子
広島へ
まだまだ、勢いよく蝉の鳴き声が響く毎日です。
原爆の被害、戦争と平和について考えようと広島平和記念資料館(原爆資料館)と平和公園の周辺に行ってきました。
原爆資料館には、亡くなった人々の遺品がたくさん展示されています。小さな子どもが乗っていた赤茶けた三輪車。家の人がお昼に食べるようにと準備した真っ黒にこげたお弁当。屋外で作業していた学生たちが着ていたこげて破れた服。そして、戦後10年たってから白血病になった12歳の少女が生きることを祈って折り続けた鶴。
展示を見ながら、強く心に残ったことの中から2つを紹介します。
1つは、被爆した人々が身に着けていた服です。破れたりこげたりしていて、多くは12~13歳の中学生たちが着ていたものです。なぜ、たくさんの中学生が犠牲になったのか…。
戦争が長引く中で、青年たちが次々と兵士として動員されていきます。国内で働く人は不足し、中学生までもが「お国のために」といろいろな作業をせねばなりませんでした。
1945年8月6日は、8000人以上の中学生が広島市中心部に集められており、多くが屋外で建物疎開(取り壊し)をしていました。暑いため上着を脱ぎ、大切な制服を木の下に折りたたんで、薄着で作業をはじめました。
8時15分。活動を開始した人々の頭上で、原子爆弾が炸裂しました。
遮るものがない屋外、薄着で作業していた人々は、地上3000~4000度の熱、秒速400mの爆風、放射線により、負傷し命が奪われました。8000人以上作業していた中学生の6200人あまりが犠牲になっています。
被爆した人々は、どんなに熱かっただろう…。どんなに苦しかっただろう…。家族のもとへたどりつきたかっただろう…。きのこ雲の下での惨状が心に迫ってきます。
これらの服には、名前が縫いつけられています。持ち主一人ひとりが生きていた証です。それを見つめながら、この子どもたちの未来を奪った原爆、そして、戦争に対して改めて怒りがこみ上げてきます。
もう1つは、白血病で亡くなった少女のベットの下から、発見された1枚の紙です。
「赤…、白…、血…。」とたくさんの数値が記されています。
家族は本人に病名を秘密にしていましたが、少女は検査後の数値を隠れて毎回書き留めていました。
12歳の少女が、自分の体調の変化に怯えながら家族に心配をかけまいと密かに記録をとり、生きることを願いながら鶴を折る…。その思いを想像すると、胸が押しつぶされそうになります。生きることへの切望と命の重みが伝わってきます。
戦後78年。時が経つと、原爆の惨状や被害にあった人々のことが記憶から少しずつ薄れていきます。
でも、遺族の方々は、「原爆投下をなかったことにしてはならない」「きのこ雲の下で起こったことを伝えなければ…」と大切な遺品を資料館に託しました。思い出すのも辛い記憶を語り続けきました。
しかし、これからは私たちがその思いをつないでいかねばなりません。広島で起こったことをしっかりと学習し、語り継いでいかねばなりません。
今、世界には12520発もの核兵器が存在し(2023年6月現在)、人類の脅威となっています。一人ひとりの声、一人ひとりの行動が、平和を築く大きな力となると確信しています。
所長 高橋 公子
平和をつなぐ
所長 高橋 公子
梅雨あけが待ち遠しい毎日です。
さて、今回は、8月6日・9日の原爆が投下された日が近づいてきました。そこで、今回は、福岡県八女市星野村で80年近くも灯され続けている「平和の火」の話です。
1945年8月6日、アメリカ軍は広島に原子爆弾を投下しました。星野村から広島に出征していた山本達雄さんは、焼け野原となった広島の町で、父親代わりだった叔父さんを探しました。しかし、叔父さんは見つかりませんでした。
達雄さんは、叔父さんの住んでいた建物の地下でくすぶっていたものに、ふうっと息を吹きかけると、火が燃え上がりました。まるで叔父さんが生き返ったようで、達雄さんは、火を星野村まで持ち帰りました。
火は、達雄さんにとって叔父さんの形見となる供養の火であると同時に、「いつかこの火でアメリカを焼き殺してやる。」と‟忌みの火”‟恨みの火”でもありました。火を見るたびに、当時の広島の惨状や原爆犠牲者の苦しみ、原爆や戦争に対する怒りなどが湧きおこり、戦後も苦悩は続きました。
時がたち、達雄さんは家族とともに火を守り続けていくなかで、やられたことばかりでなく、日本が侵略したアジアの人々のことを思うようになりました。
「こんな恨みを代弁していても死んだ人は納得するだろうか。」
「恨んでばかりいてもよくないのではないか…」
と葛藤を繰り返した後、1968年、「平和の火」として村が引き継ぎたいという申し入れを受け入れました。
その後、達雄さんは原爆犠牲者の供養をするとともに、核兵器の恐ろしさ・戦争の愚かさを唱え続けました。晩年、記者から
「何万人も一度に殺した大虐殺の兵器原子爆弾とアメリカを日本人として許せますか?」
と聞かれたた時、
「…日本人として…なかなか…。その事実は消えんけど、それは水に流す努力をせん限り、しょっちゅう殺し合いを繰り返す。一所懸命気持ちを落ち着けて、そういう恨み心は洗い落とさにゃならん。その努力だけは死ぬまで続く。」
「人間同士が殺し合う愚かなことは、もう、止めにゃあかん。」
と答えていました。
達雄さんの持ち帰った火は、今も「平和の火」として星野村で灯され続けています。また、大分県、香川県、愛知県、福島県など全国18か所に分火され灯されています。つい先日、私も、福岡の碓井平和祈念館に分火された「平和の火」を見に行ってきました。祈念館では、展示された資料や「平和の火」を分火してもらった思いをていねいに説明してくれました。
原爆を体験した山本達雄さんの平和への願いは、息子の山本拓道さんへ、そして、全国の「平和の火」を受けとった人々へと広がり、平和をつないでくれています。
戦後78年たち、戦争体験者から直接話を聞くことが難しくなってきました。しかし、体験した人々の記録、戦争当時の道具、戦争遺跡などから、戦争の事実と平和の尊さをしっかりと学ぶことができます。そして、それを次世代へつないでいかねばなりません。
わたしは、この夏、広島に行き、原爆について学習を深めてきます。
地域から平和を考える
所長 高橋 公子
ヒマワリの花が咲くのを心待ちにしながら、水やりをするこの頃です。
さて、今回は、津久見市の小さな島のことです。
私が39年前初めて勤務した学校は、津久見市の保戸島小学校でした。それまで一度も訪ねたことがなく、どんな島かと期待しながら着任しました。津久見港から船で25分、周囲が4㎞で、マグロ漁が盛んな島です。保戸島の港から小学校までの移動の途中、地域の方がたくさん声をかけてくれるとても温かい地域です。
そんな保戸島にアジア・太平洋戦争末期の1945年7月25日、アメリカ軍によって小学校(保戸島国民学校)へ爆撃がおこなわれました。
当時500人の子どもたちが教室で勉強をしていましたが、爆撃機グラマンが投下した爆弾は1年生と5年生の教室に直撃し、一瞬で多くの子どもたちの命を奪い去りました。崩れた校舎の下敷きになった子ども、戻ってきたグラマンから機銃掃射でねらわれた子ども…。またたくまに学校は地獄と化しました。
学校にかけつけた家族は、子どもたちを探し求めましたが、最後までわが子を見つけられなかった人もいました。
この日の攻撃で、子どもたちと教職員あわせて127人の命が奪われました。かろうじて生き延びることができた人や亡くなった子どもたちの家族、島の人々すべてが、体と心に大きな傷を負いました。戦後も苦しみは癒えません。なぜ、学校を攻撃したのか。なぜ、子どもたちと知りながら機銃掃射をしたのか。戦争の残虐さが突き付けられます。
今から78年前の、忘れてはならない戦争の記憶です。
実際に保戸島に行き、体験した方や語り継ぐ方に話を聞くことで、その場でしか知ることのできない戦争の事実に気づきます。感じることのできる思いがあります。その事実や思いをしっかりと受け継ぎ、これから子どもたちへと継いでいかねばならないと感じています。
みなさんの地域にも、きっと戦争や平和について考えることのできる場所があると思います。当時を知る方も少なくなってきています。ぜひ、地域の戦跡を巡ってみませんか。
ホタル
所長 高橋 公子
「ほう、ほう、ほたるこい。あっちのみずはにがいぞ。こっちのみずはあまいぞ。…」
この『ほたるこい』の童謡が心に浮かぶ季節となりました。
今回は、ホタルの話です。
わたしは、目の前が田んぼ、裏が山という自然豊かな土地に生まれ育ちました。
子どもの頃の話ですが…。田植えが始まる5月末~6月上旬、あぜ道の近くで舞うホタルを見るのがとても楽しみでした。でも、いつの頃からか、その姿を見ることはなくなってしまいました。
どうしていなくなってしまったのか、地元『ほたるの会』の方に聞いてみました。
昔、ホタルは市内全域に生息していましたが、河川工事、家庭や工場からの排水、農薬、街灯の光などの影響を受けて徐々にその姿を消していったそうです。わたしたちの生活が便利になるにつれて、ホタルは、山奥へ山奥へと移動していき、今は、限られた場所でしか見ることができなくなってしまいました。
「ホタルのあかりは幻想的で心惹かれます。減少したのはとても寂しいですね。」と話すと、『ほたるの会』の方は、「世界で2000種あるホタルのうち、光るホタルの方が少ないんですよ。」とのこと。ホタル=光るというのは、単なる思い込みだったことも分かりました。
それに、『ほたるの会』では、ホタルが急激に減少するようになって、その原因を調べたり、人工的に増やしたりする努力もしたそうです。そこで、『ほたるの会』がこれまでどんな活動をしてきたのかを質問すると、
【調査活動】
〇学校と共同で川のホタルの生態調査 〇ホタルの飼育・放流
【行政への働きかけ】
〇ホタルが生息できるような自然の環境に近づけるため、河川工事の際は、石垣にしたり、土や草原を残したりした。
〇夜間の光を抑えるため、
・白熱灯をナトリウム灯にかえる。
・ガードレールの色を光が反射しにくい色に変更する。
・公衆トイレからの光を漏らさないように窓枠を開閉式にする。
など、ホタルの棲む環境を守るために、いろいろ取り組んでいたことを知りました。
地域で開発事業をする際には、自然との共生を考えながら、豊かに発展させていってほしいと思いました。おとなも子どもも心がほっとする空間。そんな場所を少しでも多く、次世代へつなげていけたらと願っています。
今年、久しぶりにホタルを見に出かけてみようと思います。
身のまわりで…(2023.5.16)
所長 高橋 公子
田植えの準備が始まり、燕が飛び交う季節となりました。初夏の訪れを感じます。
さて、今回は身のまわりの会話から発見したり感じたりしたことを紹介します。
職場には、本棚にずらっと並んだファイルがあり、よく見ると丸い穴があいています。
今まで気にすることのなかった穴です。ファイルの下から4㎝くらいの位置に直径2㎝ほどの穴が、幅の広いファイルにも狭いファイルにもついています。「どうして穴があいているんだろう?」
「飾り?」「中が見えるように?」…くらいしか思いつきませんでした。実は、その穴は、「ファイルを取り出すために指を入れる穴」でした。今まで、棚に隙間なくファイルを並べるような必要がなく紙のファイルを使うことが多かった私は、穴がある便利さに考えが及びませんでした。
なるほど…。身のまわりには、使う人のことを考えて工夫されたものがいろいろあるんだなと思いました。
では、「図書館の本を取り出すときはどうしていただろう。」と振り返ってみました。図書館の本には、便利な穴はあいていません。本に隙間があれば、本の背の上の部分を引っ張って出さずに、本の両脇を持って取り出します。でも、本がぎっしり詰まっている時は? と考え込んでしまいました。
う~ん、図書館の本棚はそんなにぎゅうぎゅうじゃなかったような…。でも、実際にはそんな場もあるなぁ…。
正しい取り出し方は、「本の背の上の部分を押す」でした。上の部分を押すと背の下の部分が飛び出してきます。そうすると、本の両脇を持つことができます。
子どもたちに本の取り出し方を伝えるとき、「本が傷むので、背の上に指をひっかけて取り出したらだめだよ。」と伝えるだけでなく、「ぎゅうぎゅうに本が詰まっている時は、…する方法があるよ。」と具体的に伝えたり考えさせたりすることが大切だと感じました。具体的な方法を知り納得して身につけることができれば、図書館だけでなく本屋さんでも本を大切にする姿勢が生まれます。学びを日常につなげることができます。
見慣れたものでも、新たな発見があります。その中には、知恵や工夫がたくさん詰まっています。いろいろなことに注意を向けて、新たな発見を楽しんでいきたいと思います。
憲法記念日を前に(2023.5.2)
所長 高橋 公子
5月の連休となりました。満開のツツジや道端のアザミに心躍ります。
さて、5月3日は憲法記念日です。『日本国憲法』は、国の最高法規です。今回は、『憲法』の平和主義について少しだけ話題にできればと思います。
『日本国憲法』は、わたしたち主権者が、時の政府に対して縛りをかけるものです。権力をもつ側が自分勝手なことをして、国民の自由を奪ったり命や生活を脅かしたりすることのないように、国家に対して、「~してはいけない」「~しなくてはいけない」と命じています。憲法は、わたしたち国民を守るという大切な役割を果たしています。
かつて多くの人々の命が奪われたアジア・太平洋戦争。その反省から、「二度と戦争という過ちを犯すことのないように」と平和な世界を願い、『日本国憲法』はつくられました。
しかし、近年、戦争の危機感を煽る報道が多く流されています。防衛費拡大・防衛力強化を容認してしまう空気が広がってきていることを非常に危惧しています。
ひとたび戦争が起これば、国民の命が犠牲になることは避けられません。そして、終わるのが困難なことも今の世界情勢から明らかです。戦争にならないための外交の努力こそ、政治の責任です。
不戦を誓った「憲法九条」をこれからの世代にしっかりと引き継いでいきたいものです。憲法記念日を前にして、この機会に憲法について調べたり考えたりしてみてはどうでしょうか。
第2章 戦争の放棄 第9条【戦争の放棄、軍備および交戦権の否認】 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦 争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に これを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦 権は、これをみとめない。 |
職場のカレンダー(2023.4.17)
所長 高橋 公子
教育総研に勤務はじめて2週間が過ぎました。朝の通勤時の楽しみは、日々変わる自然の様子。これまでは、津久見島や干潟など海の景色を見ながらの通勤でしたが、4月からは桜や藤の花・新緑など山の景色の変化に心を弾ませて車を走らせています。
学校を退職して、ふと、これまでの教員生活を振り返ってみました。学校へ向かう車の中では、「今日1日、楽しい授業ができるかなぁ…。●●の仕事を終わらせないと…。」などとその日の授業の流れと自分の動きイメージしていました。実際その通りに過ごせる日はほぼ皆無。毎日起こる何かしらの出来事が優先となり、帰りには大量のノートや翌日の授業の準備物を抱えて、車に乗り込む毎日でした。
さて、今回の小部屋は「元号」についてです。
職場に掲示しているカレンダーを見ると、2023年、令和5年、平成35年、昭和98年と4通りの表記がされていました。なぜ、こんなにたくさん??
2023年(西暦)だけでもよさそうなのに…。西暦であれば、年齢を計算するときに便利だし、ほかの国でも通用する良さがあります。
そもそも、なぜ元号を使用するのでしょうか。
元号は、古代中国で始まった習慣で、時の皇帝の権威を示すために利用されました。それが、日本をはじめアジアの国々でも使われるようになりました。日本の元号のはじまりは、7世紀ごろからと言われています。
その後、元号は、1889年明治時代の旧皇室典範に規定され法制化されました。天皇制と結びついており、戦争中には国民の戦意高揚のために利用された歴史があります。敗戦後の1947年、新憲法施行に伴って現皇室典範が制定され、その中に元号は明記されませんでした。法律上「元号」を使用する根拠はなくなりした。それなのに、政府は元号が国民に広く浸透していることを「事実たる慣習」として、政府・官公庁で元号を使い続けました。
その後、元号を取り巻く論議も起こりましたが、1979年に「元号法」を成立させました。
元号法
1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。 |
という短いものです。
「元号法制化」の議論の中で、『元号についての政府の基本的見解』によると、
・元号法は、一般国民に元号の使用を義務付けるものではない。
・現在、我が国における年の表示方法として西暦もあるので、西暦でも受理する。
・地方自治体に対しても、元号を強制することはできない。
と答弁しています。つまり国民に対して、強制や義務ではなく、協力要請ということなのです。
最近、役所関係の書類などでは元号を使うように言われることが多いという声も聞きます。「どうして西暦ではだめなのか」「だれが、だめだと言っているのか。」など気になることは、納得できるまで追究することが大切だと思っています。
曖昧にすることや妥協することを重ねていると、気づかないうちに大きな波に呑み込まれ、おかしな方向に向かわされていく危険性が高まります。「いつか来た道」(戦争への道)を繰り返さないために、アンテナを高く伸ばし、声に出す(行動につなげる)ことを大事にしていきたいものです。
人と人、学びと学びを つなぐ
所長 高橋 公子
これまで、臼杵・津久見の子どもたちと38年間過ごしてきました。わたしにとって教室は、そこにいるだけで不思議と元気が湧いてくる場所でした。疲れがちょっと残っている朝も、「おはよう」と子どもたちとあいさつを交わすだけで、心と体にスイッチが入ります。授業から、子どもとの会話から、新たな発見や気づきがたくさんあり、自分を見つめ直す機会を与えてもらいました。学校を出て学ぶことも好きなので、地域にでかけ、人々と出会い、地域の魅力や歴史を肌で感じる、そんな学びを楽しんできました。子どもたちの多様な反応にわくわくし、子どもたちの瞳がきらきらっと輝く瞬間、「この仕事を選んでよかったなぁ」と感じることができました。これまで出会ってきた子どもたちに感謝の思いでいっぱいです。
教研では、平和教育分科会に所属してきました。フィールドワークを大切にしながら、その場で体験者が語ったことや戦跡から自分自身が感じたことを、どのように子どもたちに出合わせ、どう学ぶのかを、なかまとともに考えとりくんできました。平和の種をまき、平和への熱をつなぐこと、それが一番の願いです。
しかし、近年学校現場では、「学力向上」の名のもとに、教職員に同じ方向を向くように要求され、一つの価値観で子どもたちをしばり、温かさや寛容さが奪われています。子どもたちも教職員も、悲鳴をあげている、そのように感じています。「やってみたいことはいっぱいある。でも、今週…がある。」と教職員は日々の対応に追われ、話したり新たな教材を発掘したりする時間も、挑戦する心の余裕もない状況に追い込まれています。平和を取り巻く状況についても、近隣の国々に対して危機感を煽る報道が頻繁に流され、「もっと備えなければ…」と人々の意識が傾きかけているのではないかととても危惧しています。始めることは容易く、終わることは難しいのが戦争です。「戦争にならないための努力を続けていかねばならない。」その思いはみんな同じなのに、学校現場では子どもたちと平和を学ぶエネルギーがもちにくくなっています。
教育総研は、2018年の設立から6年めを迎えました。教育総研の目的は、
【教育総研の目的】 憲法・子どもの権利条約に基づく民主教育の確立に寄与するため、教育問題に関する理論的、実践的研究および調査活動を行い、その成果をふまえ教育研究活動を推進し、教育条件の整備に寄与するとともに、広く提言を行うこと |
とあり、とても大きな役割をいただいたと感じています。
今、教育に関して、「教職員の働き方」「子どもの権利」「教育費」「平和教育」など課題が山積しています。その教育現場にいる子どもたちの、そして、教職員の笑顔を思い浮かべながら、少しでも学校の「助け」となるよう努力していきます。「人と人をつなぎ、学びと学びをつなぐ」ことを意識しながら、総研のとりくみを充実させ、広げていきたいと思っています。どうぞ、ご支援ご協力を、よろしくお願いします。